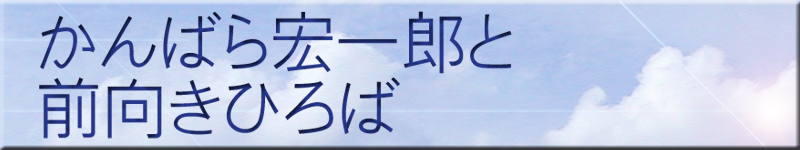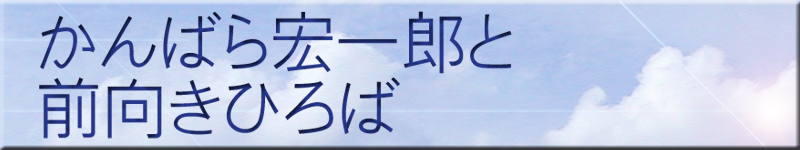���@�Q���ڂ́A�����s�ɍs���A�s�o�Z��ɂ��Ċw�т܂����B


�܂��A�����s�̕s�o�Z�̌�����f���܂����B

�����s�ł��s�o�Z�������k���͑����X���ɂ���A���ɃR���i�Ђő����̐������������Ƃ̂��ƁB
�Ƃ͂����A�ߘa�T�N�x�̕s�o�Z�o�����͏��w�Z�łP�D�O���A���w�Z�łT�D�P���ƁA�S���̏��w�Z���ςQ�D�P���A���w�Z���ςT�D�P�����͒Ⴂ�ɂ���܂��B
�����s�̕s�o�Z��Ƃ��ẮA����x���Z���^�[�i�A�E�g���[�`�E�I�A�V�X�����j�̐ݒu�A���k�w���x�����̐ݒu(�s���̋K�͂̑������w�Z�U�Z)�A�s�ꑮ�̃X�N�[���\�[�V�������[�J�[�̔z�u�AICT�����p�����I�����C���w�K�x���A�w�т̑��l���w�Z�������̐ݒu����Ȃ��̂ł��B
����x���Z���^�[�́A�Ƃ���͏o�邱�Ƃ͂ł��邪�A�w�Z�ɓo�Z�ł��Ȃ��s�o�Z�y�ѕs�o�Z�X���̏�Ԃɂ��鎙�����k��ΏۂɁA�s���R�����i�T�e���C�g�����Q�������܂ށj�ɊJ�݂���A���Z�����U������v�N�x�C�p�E���Ƃ��Ĕz�u���A�w�Z�Ŏg�p���Ă���e���Ȃ̃v�����g�Ȃǂ��g�����w�K��N���G�[�V�������s�Ȃ��Ă��܂��B
�\���l���͏��w�����Q�A�R���قǁA���w���͂R�O�`�S�O���قǂł����A�\�������ŗ��p���Ă��Ȃ��������k����萔����Ƃ̂��Ƃł����B
���p�҂���́A�����K�����������A���������ł���悤�ɂȂ����A���������C�����ɂȂ�����A�l�Ƙb���������������邱�Ƃ��ł����Ƃ������O�����Ȉӌ�������Ƃ̂��Ƃł����B
�I�����C���w�K�x���́A�w�Z�ɂ�����Z���^�[�ɂ��ʂ����Ƃ��ł��Ȃ��������k��ΏۂɁA�s���F��]���w�Z���ɃX�^�W�I��ݒu���A���Z�����S������v�N�x�C�p�E���Ƃ��Ĕz�u���AAI�h���������g�����ʊw�K��w�K���掋���ɂ�鋳�Ȃ̊w�K�A�e�[�}�Ɋ�Â����ӌ������A�O���u�t�ɂ��u�a�Ȃǂ��A���p�������k�͈�l���^�u���b�g��p���āA�������܂��B
�I�����C���w�K�x���o�^�Ґ��́A�T�˂Q�O�`�R�O�l���炢�ł��B
���̎��Ƃ̎Q���҂���́A�O��������������ł���悤�ɂȂ����A�F�X�Ȃ��Ƃɋ��������Ă�悤�ɂȂ����A�l�Ɗւ�邱�ƂɐϋɓI�ɂȂ����Ȃǂ̐����������Ă��Ă���悤�ł��B
�Ō�ɁA����̎��@�̃��C���ł�����w�т̑��l���w�Z�u�F��]�����v�͍��N�x�i�ߘa�U�N�x�j�A�J�n���ꂽ����̎��ƂŁA�Ƃ���o�邱�Ƃ͂ł��邪�A�ݐЂ���w�Z�ɓo�Z�ł����F��]�����̏��l���w���Ŋw�т����Ƃ����ӎv�����鐶�k���ΏۂŁA���w���e�w�N�P�O�����x�i�v�R�O�����x�j���W���A�v�P�P�l���ݐЂ���Ă��܂��B
�ݐА��k�́A����x���Z���^�[����P���A�I�����C���w�K�x������Q���A�����w�Z����Q���̓]���҂ŁA�P���̓t���[�X�N�[���ƕ��p����Ă���Ƃ̂��Ƃł����B
�Ȃ��A���̌F��]�����́A�אڂ��鉄���s����Y���w�Z��1�̋����ŊJ�݂���Ă��邱�Ƃ���A�������͉̂����s����Y���w�Z�w�т̑��l���w�Z�������u�F��]�����v�Ƃ̂��Ƃł����B
�F��]�����́A�u�q�ǂ��������w�Z�ɍ��킹��v�̂ł͂Ȃ��A�u�w�Z���q�ǂ�������l��l�ɍ��킹�Ă����v���Ƃ�A���҂Ɣ�ׂ邱�ƂȂ��A�������g���ɂ���q�ǂ������̈琬�A�V���Ȏ����̉\���������邱�Ƃ��ł���q�ǂ������̈琬��ڎw���Ă����܂����B
�E���z�u�Ƃ��ẮA���w�Z�̕������Ƃ����ʒu�t���̂��߁A�Z���A�����͓�Y���w�Z�Ɠ����ŁA���@�P���A��u�t�P���A��v�N�x�C�p�E���Q����z�u����ƂƂ��ɁA��Y���w�Z�̐E�������ȒS�C�ɔz������Ă��܂����B
�܂��A�s���ςɒS�����劲�P���A�s����ʋ���x�����P����z�u����Ă��܂����B
�܂��A�w�т̑��l���w�Z�͎��Ǝ����⋳�Ȃ̕ύX��V�݂��F�߂��Ă��邱�Ƃ���A���Ǝ����́A�W���̂P�O�P�T����/�N�ɔ�ׂ�Ƃ��Ȃ�]�T�̂���V�V�O����/�N�Őݒ肳��Ă���A����ɋ��ȂɂƂ��ꂸ�ɒT���I�Ȋw�т�i�߂�v���W�F�N�g�w�K��A����̃R���g���[���A�X�g���X�}�l�W�����g�A�F�m�̘c�݂̏C�����w�ԃZ���t�}�l�W�����g�Ƃ��������Ȃ��V�݂���Ă��܂����B
�F��]�����ɂ��ẮA�ΐl�W�ȂǍݐА��k�ɑ傫�ȕω���������ƂƂ��ɁA�ی�҂�n��ɂƂ��Ă��D�e��������A���E���̎�������ɂ��Ȃ���Ȃǂ̌��ʂ��o�Ă���Ƃ̂��Ƃł����B
����ɍݐА��k��ی�҂���̕]�������Ȃ荂���悤�ŁA���p���k���͂���قǑ����͂Ȃ����̂̕s�o�Z���k�̎M�ɂ͂Ȃ��Ă���悤�Ɋ����܂����B
����A�萔�݂̂̐E���z�u�ł͉^�c������Ȃ��ƁA����ے��ɍX�Ȃ�H�v����P���K�v�Ȃ��ƁA�ݐА��k�̑��ƌ�̒ǐՁA�J�Z�����̎v���̌p���Ȃǂɉۑ肪����Ƃ̂��Ƃł����B
�Ȃ��A�F��]�����̐����ɂ������p�́A���̕⏕�������p�����Ƃ̂��Ƃł������A�C�U��P�S�Q���~�A���Օi��R�U���V��~�A���p����S�Q���V��~�A�萔���P�R���W��~�̍��v��Q�R�T���~�ƁA�^�c�ɂ������p��X�O���~�ŁA���Ȃ�����Ɋ����܂����B
�L���s���w�т̑��l���w�Z(�s�o�Z����Z)�̐ݒu���v�悳��Ă��܂����A�܂��́A�s�o�Z�������k�̂��ڍׂȎ��Ԓ�����j�[�Y�̔c���A���Ԃ̃t���[�X�N�[���Ƃ̊W���Ȃǂɂ��Ă̒����������K�v�Ɗ����܂������A���܂��K�͂Ȑ��������邱�Ƃ͔����������ǂ��悤�Ɏv���܂����B
���Ȃ݂ɁA�����s���ݒu���Ă��鑽�l�Ȋw�т̏�ł���F��]�����A����Z���^�[�A�I�����C���w�K�x���͑S�čZ���̔��f�ŏo�Ȉ����ɂȂ����A���Ԃ̃t���[�X�N�[���ɂ��Ă͏o�Ȉ����ɂ͂Ȃ�Ȃ��Ƃ̂��Ƃł����B

�����̒��́A�u�r�w�O���Ȃ���ʐM�Q������z��\��ł��B
|
��
2025/2/3�@ �@�s��s���}���ق����@�@
|

�����́A�L���w�O���Ȃ���ʐM�Q������z��܂����B �X���������I����ƁA��}���ŁA��㍑�ۋ�`�ɍs���A��h���@�ɎQ�����܂����B

���@�P���ڂ́A�{�茧�s��s�ɍs���A�s��s���}���ق��܂ޒ��j�{��(Mallmall�F�܂�܂�)�ɂ��Ċw�т܂����B
 
�܂��A���j�{�ݑS�̂̈��́uMallmall(�܂�܂�)�v�Ƃ́A�l�X���W���A�l�X�Ȋ������J��L����ꏊ���w���uMALL�v��2�d�ˁA�u�܂�܂�v�Ɠǂނ��ƂŁA�Ⴂ����ɂ��e���݂������Ă��炦��_�炩����\�����A���j�{�݂��������s���ۂ̉C�ނ��ƂŁA���L������̎s���Ɉ����������Ă��炤���ƂŌ��肳�ꂽ�Ƃ̂��Ƃł����B �s��s�ł́A���S�s�X�n�ɂR�X�܂������S�ݓX���^�X�[�p�[�������T�N(�P�X�X�R�N)����̂P�O�N�ŋƎ�]����|�Y�ɂ��P�X�܂ɂȂ�A����ɍx�O�^��K�͏����X��(�V���b�s���O���[��)�⊲�����H�����̃��[�h�T�C�h�^�X�܂̋}�������҃j�[�Y�̑��l���Ȃǂɂ��A�Ō�̒��j�X�܂������u�s���ہv�������Q�R�N(�Q�O�P�P�N)�ɕX���܂����B �����ŁA�s���ۂ̐Ւn�Đ����܂ߒ��S�s�X�n�̊��������ۑ�ƂȂ�A���j�{�ݐ����Ɏ���܂����B ���S�s�X�n���j�{�ݐ����̌v�����Ɍ����ẮA�s���ӌ����Ȃ����c��[�N�V���b�v���d�ːi�߂��A�s��s�͐V���Ȓ��j�{�݂̐����R���Z�v�g�̈�Ƃ��āA�s���j�[�Y�ɑ������{�݁E�@�\�̏W����f���A�}���ق̈ړ]�����A�q��Đ��オ�W���A�𗬂ł����Ԑ����A�s���𗬃X�y�[�X�̐����{��(�s�����W���A�y���݁A�𗬂��銈���𐄐i���邱�Ƃ�ړI�Ƃ����{��)�̐����A����I�ȓ��킢��n�o���鑽�ړI�L��̐��������肳��܂����B �܂��A���j�{�݂̐����̃R���Z�v�g�Ƃ��āA�����������̊��p�ɂ�鐮���R�X�g�̏k�����f���A����ۃZ���^�[���[����}���قɃ��m�x�[�V�����ɂ����C���s���A���K�͐}���ق̐V�݂Ɣ�r���Ė�R�P���~�̐����R�X�g�k���Ƌ��s���}���ق̖�R�{�̃t���A�ʐϊg�����������܂����B �}���ق̐����ɂ������ẮA�W�q�͌���̎�g�Ƃ��āA���{�v�ƕ��s���A�}���ق̋�ԓI�������Ɩ�(�Ƌ�E���i���̃f�U�C���E���C�A�E�g�E���B��������ւ̏���)�A�w��Ǘ��Ɩ��A�J�t�F�̗U���E�^�c�Ɩ��̂R�ϑ��Ɩ����p�b�P�[�W�ɂ��A��̓I�ɒS�����Ǝ҂�����^�v���|�[�U���őI�肳��܂����B�Ǘ��҂��i�K����֗^�����邱�ƂŁA�����Ȑ݂��ƊǗ��^�c�̉~�����A���p�Җ����x�̌����}��A�z��ȏ�̗��َҐ�����������܂����B
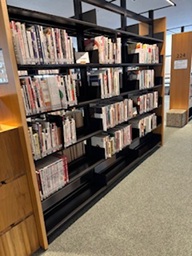 
���ۂɊٓ������w����Ɛ��I�m�E�n�E�����������f�U�C���E���C�A�E�g�̍���������������Ƌ��ɁA�}���قƈ�̊��̂���u�u�b�N�J�t�F�v���͂��߁A�ٓ��ł̉�b�̋֎~����H�̋֎~�Ƃ������Œ�T�O�̌������ɂ��{���D���Ȑl�ȊO�ł��K�ꂽ���Ȃ�悤�ȋ��S�n�̗ǂ����ꏊ�A��Ԑ���������Ă���A�ƂĂ��D���������܂������A���ۂɎs���̕]���┽�������ɗǂ��Ƃ̂��Ƃł����B ����ɁA���Ƃ��ƃV���b�s���O���[���������Ƃ�������m�x�[�V�����������Ƃ��A�N��������₷���ꏊ�ɂȂ�₷�������Ƃ̂��Ƃł������A�}���ٗ��p�҂̂P�`�Q���͎s�O�⌧�O����̕��Ƃ̂��Ƃł����B �܂��A��������T�T��������ɂ�������炸�A��P�V�����������˂ɒu���Ă͂��Ȃ����A����́A�]���Ƃ̐}���قƈႢ�A�L�X�Ƃ�����Ԃ����A�u�{�ł͂Ȃ��A�l������v���ӎ����Ă���Ƃ̍l�����ɂ́A�V���Ȏ��_��C�Â�������܂����B ���Ȃ݂ɁA���˂ɒu���{�̐��͏��Ȃ߂����A�E�����Q�A�R�������ɖ{�����ւ��Ă����A���p�҂���́u��ɐV�����}���فv�Ƃ̕]����ӌ�������Ƃ̂��Ƃł����B ����̎��@�ɂ����āA�{�݂̓������Ԃ̊��p���@�Ȃǃn�[�h�ʂ͂������f���炵�������ł����A���̃x�[�X�ɂ͎s�Ƃ��Đ}���ق̐����ɂ������Ă̗��O�⏫���I�ȃr�W�������������肵�Ă����邱�ƁA�������}���ق̐�����^�c�Ɋւ���Ă�������X�̃A�C�f�A��v���̋������Ȃ���ΐ������Ȃ������ł��낤�Ɣ��ɋ��������܂����B �{�s��(����)�����}���ق��͂��߁A����̐}���ِ�����^�c�ɂ���ɕK�v�ȗv�f�ł��邱�Ƃ��ĔF���A�Ɋ����܂����B
|
��
2025/2/2�@ �@�Ǝ���������A�q�ǂ������ƗV��
|

�����͎���̑|�������A��T�ԕ��̔������ȂljƎ����܂Ƃ߂Ă��܂����B �ߌォ��́A�q�ǂ������ƌ����ɍs������A��������̉�h���@�̏�����\�K�������肵�܂����B �����̒��́A�L���w�O���Ȃ���ʐM�Q������z��\��ł��B
|
��
2025/2/1�@ �@�n�悱�ǂ������ł̖쒹�ώ@��ɎQ���@
|

�����͌ߑO���A��쏬�w�Z�̒n��q�ǂ������ł̖쒹�ώ@��Ɉ��S�Ǘ��̂���`���Ƃ��ĎQ�����܂����B

�����T��ʂ�Ƃ��Ɍ��Ă���ƁA�قƂ�ǒ������Ȃ��悤�Ɋ����Ă��܂������A���߂��ł�������T���ƁA�������N�Ɠ������炢�̎�ނ̒����ς邱�Ƃ��ł��܂����B

�Q�����������������A���Q�����o�ዾ��]�������g������A�}�ӂ��J���Ē��ׂ���ƁA�y���݂Ȃ������������Ɗώ@�����Ă���Ă��܂����B �ߌォ��́A�x�c��قɍs���A���A��������̖�����ɏo�Ȃ��܂����B
| | |